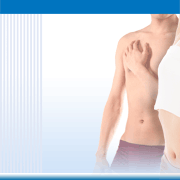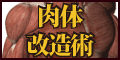常駐させてもめちゃくちゃ軽快に動作する「バスケ」
こんにちは。
自分開花起業プロデューサー、
癒さない魔法のセルフイメージアップの専門家、
堅田不二子です。
私の半世紀に渡るストーリーをこれから、お話していきますね。
私は、1960年代に、秋田県秋田市に生まれました!
家は、祖父の代から靴の卸売業と小売り業を営んでいました。
父は、子供の頃から頭が良くて、東京大学まで進学したのですが、
体が弱く、大学時代に結核になり、やむなく秋田の実家へ
帰ってきたという経歴。
母は、秋田市内の老舗の仏壇屋の次女。
やはり、東京の短大に進学したものの、実家へ戻り、
花嫁修業中に父から熱望されて、嫁いだという経歴。
私は長女で、年子の弟がいます。
家は商売で忙しく、お店と家がつながっていたので、
私は幼少期から、お手伝いさんのお姉さんと行動していました。
母は、いつも父の傍で、働いていたのです。
元々、父はあまり商売に向いていない性格だったので、
お店を閉めて、家に帰ってきても、機嫌が悪いことが
多かったです。
機嫌が良いときは、酔っ払って、私に
飛行機をしてくれたことを、よく覚えています。
しかし、機嫌が悪いと、
私が、テレビを観ていても、
「こんなくだらない番組は見るな!」と、消してしまったり、
「世の中、バカばっかりだ!」とか、
「人間はズルいやつばかり・・・」とか、
ネガティブな発言ばかりしていました。
父の機嫌が悪いと、怒鳴られるので、
祖母も母もいつもピリピリしていたと
記憶しています。
私は、そんな、家庭の雰囲気が嫌でした。
なので、父が帰ってくると、そそくさと
自分の部屋へ行き、本を読んだり、
絵を描いたりして、空想の世界へと
逃避していました。
小学校に上がると、父の仕事は忙しくなりました。
秋田市の駅前にできた、ショッピングセンターに
支店を出したのです。
それに伴い、母も忙しくなり、
私は、学校から帰っても、家には祖母しか
いませんでした。
それで、ますます、私は家に帰るのがつまらなくなって
いきました。
小学校では、陸上部、合唱部、バスケットボール部と
部活を掛け持ちして、夕方まで、家に帰りませんでした。
父は、一度も、参観日や運動会に来てくれたことは
ありません。
家族で旅行に行くことも、ありませんでした。
そんな、家庭環境で、私は、徐々に
空想の世界で遊ぶのが大好きな少女になっていったのです。
続きは、こちらの記事
***************************
2020年より、LINE@を始めることにしました。
LINE@にご登録くださいますと、
私から、音声メッセージなどのプレゼントを
お受け取りいただけるようになります。
また、私と1対1のお話もできるようになりますので、
ぜひ、お友達になってくださいね!
ご登録されたら、私から、起業する際によくある
疑問などにお答えする無料音声などを
プレゼントいたします!
*******************************
バスケのカラクリを実際に検証してみた
愛の力って、凄いね
もう、そんな事言わないの!
だって、初めての模試で、満点だよ?たしかに、範囲は狭いらしいけど、俺だったら、あり得ないよ
トクマンは、敬愛する先輩の偉業に、感心しながらも、
『人間じゃないな』
とも思う。
今の彼が、『本気』なら、これまで成均館大創立以来の天才と呼ばれていたバスケ部時代は、一体何だったのか?
あの時でも、既に、ヨンに並ぶべき者が居なかったと言うのに、全力で走り始めた彼に、誰が追いつくと言うのか?
「先輩のポテンシャルにもビックリだけど、それだけやる気にさせるねーさんを、誇りに思うよ」
神妙に頷く弟に、ウンスは、恥ずかしさしか感じない。
「その話は、もう、おしまい!ほら、ケーキ、傾けないで!」
チェ家の玄関先で、仲の良い姉弟は、少々緊張気味だった。
一泊お泊まりセットを1つのリュックに詰め込み、背中に負わされたトクマンは、手に持つ箱の水平を保つように、姿勢を正す。
中身は、モンブラン、紅茶シフォン、レモンパイ、フルーツたっぷりのゼリーなど、人数分以上のケーキがたっぷりと入っていた。
一宿一飯の恩義。
と言うには、あまりにも甘く可愛いお礼の品だが、甘い物好きのトクマンに選ばせたら、こんな風になってしまった。
「じゃぁ、押すわよ」
正門に付けられたインターフォンのスイッチを、ウンスが押そうとしたのと、門が開いたのは、同時だった。
「「わっ!」」
二人して仰け反る姉弟の目の前には、申し訳なさそうな顔のアジュマ。
「申しございません。その・・・奥様が、見てこいと・・・」
ウンス達の到着が待ちきれないジャオクは、頻繁にアジュマに問うたらしい。
『まだ、来ないの?』
約束の時間まで、まだ、十分前。
でも、アジュマは、もう六回は、玄関を見に来ていた。
「どうぞ、中へ」
外玄関を開けると、中には、程よい広さの芝生が敷かれた庭。
ジャオクが家に居ても景色が楽しめるように、ウォンジクが、庭師に手入れをさせている。
石畳の小道を真っ直ぐ抜けると、内玄関。
ドアを開けると、奥から、
「来てた?」
とジャオクの声がする。
「来ました」
トクマンが返事をすると、パタパタとスリッパで走る音が聞こえた。
「待ってたわー」
小走りに駆け寄ると、ジャオクは、ウンスの両手を握って、上下に振った。
「今晩は、アジュマが、たーくさんご飯を作ってくれたから、いーっぱい食べてね」
「あ、ありがとうございます」
ダイエット、ダイエットと叫ぶ今時女子と違い、ウンスは、モリモリ食べる。
それで太らないのだから、余程体を動かしているのだろう。
ただ、面と向かって大食漢だと言われているようで、ウンスは、少し恥ずかしかった。
「俺も、たーくさん頂きますね!これ、お土産のケーキです。これも、いーっぱい買ってきました」
ニコニコ笑いながら、箱を持ち上げて見せるトクマンに、益々ジャオクの顔が綻ぶ。
「トクマン君の食べっぷりが、又、見られて嬉しいわぁ」
「ありがとうございます!ケーキ、台所まで持っていきますね」
トクマンは、スタスタと、勝手にキッチンへと消えてしまった。
残されたウンスは、
「ウンスちゃんは、こっち!」
ジャオクに手を引かれて、居間へと強制的に連れて行かれる。
フフフフフ
アジュマは、微笑みながら内玄関を閉めた。
また、この家に、太陽が帰ってきた。
かっ、可愛い!
でしょー、そうでしょー、もう、本当、女の子かと思うくらいでしょー
ジャオクは、自慢げにヨンの幼い日の写真をウンスに見せた。
クリクリお目目に、プックリしたホッペと唇。
フワッと風に揺れる髪が、今にも動き出しそうで、ウンスは、そっと写真に触れた。
「私は、体が弱いから、なかなかヨンと遊んであげられなかったの。だから、せめて、写真に残してあげたいって思ってね」
ジャオクは、元々センスがあるのだろう。
構図が、プロ並みに上手い。
そこに、子どもへの愛情と、被写体の愛らしさが加われば、鬼に金棒だ。
どのページをめくっても、可愛いヨンしか出てこない。
それが、居間に、何十冊も溢れかえっている。
ただ、残念なのは、小学校に上がってからは、入学式、運動会、卒業式くらい。
日常のヨンは、どんどん少年から青年になり、母親のカメラに向かって笑う事は無くなっていた。
「将来・・・ウンスちゃんとヨンの間に子供が生まれたら、私が撮ってあげますからね」
「・・・・はぃ」
ウンスにとって、結婚などと言うのは、まだずっと先で、現実味のないもの。
でも、ヨン以外の男性も考えられない。
ウンスが、薄っすらと頬を赤く染めて頷く姿に、ジャオクは、何度も何度も頷いた。
つづく
ヨンの赤ちゃん時代・・・たまらん。